
レアとおぼしきサントラを勝手気ままに紹介していく『このサントラ、ちょっとレア。』 本日はこれから鎌倉市川喜多映画記念館にて映画『戦争と平和』(1947)の登壇解説をさせていただく、志田一穂がお送りいたします。

さて、本日8月15日、戦後80年という大きな区切りを迎えた終戦記念日でございます。昭和天皇が玉音放送を全国に発信した正午、その同じ時間に今回のコラムもアップいたしました。そんなわけで今回はあえて戦争をテーマにした映画たちから、この機会にこそ聴いてほしいサウンドトラック、紹介していきたいと思います。
まずはクリント・イーストウッド監督作品『アメリカン・スナイパー』(2014)です。

イラク戦争において、ネイビー・シールズ史上最強の狙撃手という異名をとっていたクリス・カイル。彼の半生を描いたのが本作です。4度も戦地へ送り出され、多くの敵国の兵士やスナイパーを狙撃してきたクリスは、除隊後シェルショック(心的外傷ストレス障害/PTSD)に苛まれるも、退役軍人社会復帰プログラムの指導者として現場復帰。しかし、皮肉にも自分が指導していた退役軍人によって射殺されるという、最悪な終幕を迎えてしまうのです…。
本作で使用されている音楽ですが、当時観ながらその旋律を聴いてハッとさせられました。これはエンニオ・モリコーネの楽曲ではないか、と。調べてみると本作にてやはりモリコーネの曲、しかも他映画作品のサウンドトラックを引用していたことが判明。その曲は、イタリアのマカロニ・ウェスタン映画の傑作、『続・荒野の1ドル銀貨』(1965)のサントラ曲。棺を埋葬する葬式のシーンにて奏でられた「The Funeral」でありました。

この曲、まさにアメリカン・レガシーを讃えるかのようなトランペット・ソロの、哀しき、しかし勇ましさをも感じられる名曲なのです。『アメリカン・スナイパー』のラストにこの曲が引用されたわけですが、国や兵士へのリスペクトのサウンドなのか、あるいは争い=戦争そのものへの戒めの旋律なのか、このモリコーネの鎮魂曲を、イーストウッドはどのように考え、あえて本作にジョイントしたのか。とても興味深いところであります。
一方、本作『アメリカン・スナイパー』にはクリスの結婚式のシーンにて、ヴァン・モリソンの名バラッド「Someone Like You」(1987)が印象的に流れます。
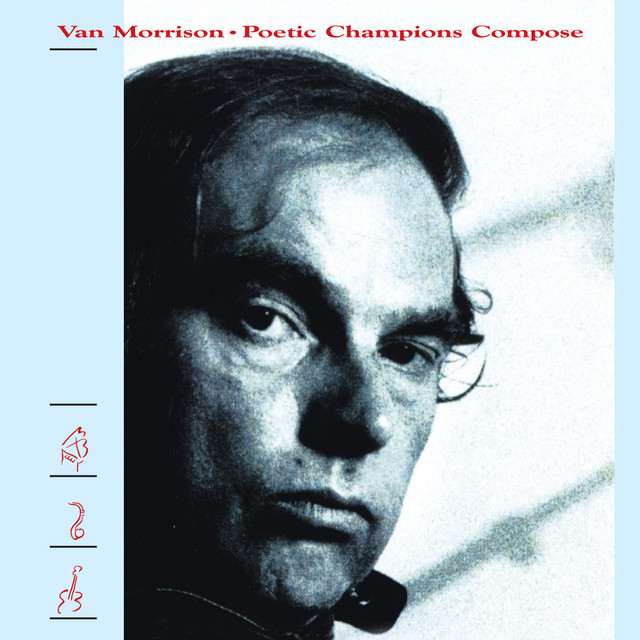
戦地での狙撃手という、宿命の十字架を背負ったクリス・カイルの心を、ただひたすらにこの歌が癒しているかのようなシーンでした。こちらでは、もそんなイーストウッドの心情が受け取れたりしたのでした。
続いては、70年代はじめから90年代まで続いたと言うカンボジア内戦が舞台となったノンフィクション作品『キリング・フィールド』(1984)です。
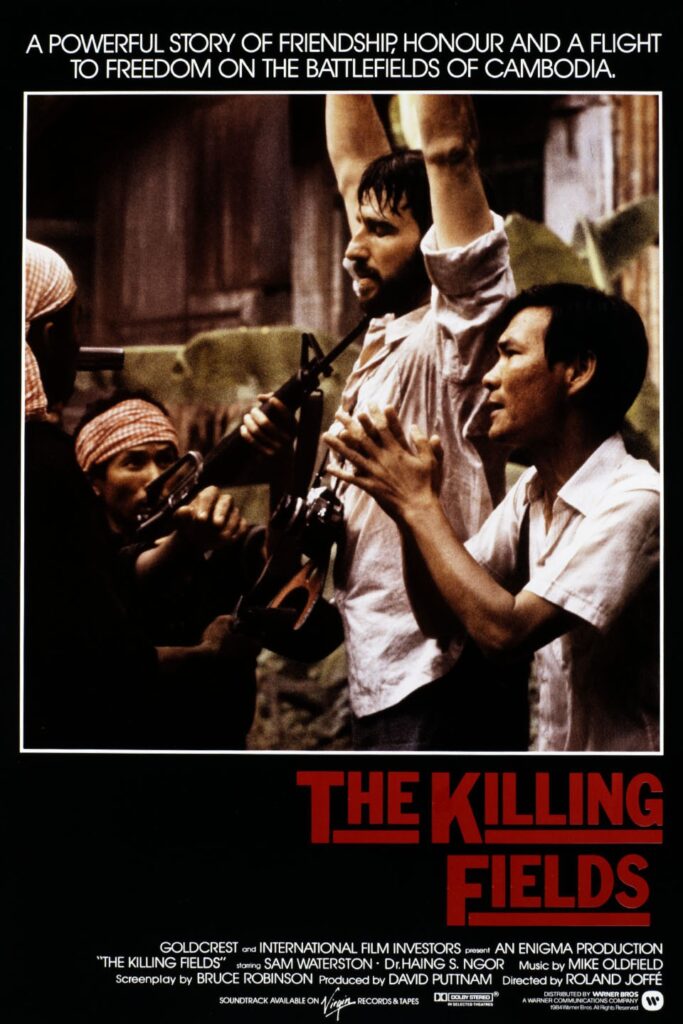
1973年、この頃のカンボジアで勢力を拡大していたのはポルポト派のクメール・ルージュ(赤色のクメール)という武装集団で、新聞記者のシドニーと、現地の通訳スタッフ、ディス・プランは、この過激化していった内戦に巻き込まれ、やがて離れ離れになってしまいます。なんとか本国に戻れたシドニーはクメール・ルージュに捕らえられてしまったプランを必死になって探し回ります。そして遂に、武装集団から逃れ、長い道のりを逃げ続けてきたプランの生存を、シドニーは確認するのです。
本作には70年代前半当時のヒット曲が、現地カンボジアのラジオから流れてくるシーンとして描かれ、それによって時代背景が映画の中から感じられたりしていました。ポール・マッカートニー&ウイングスによる「Band On The Run」と、ジョン・レノンによる「Imagine」がそれらであり、戦地でありながら軽快に空気を揺らすポールのロック・チューンと、ジョンによるただただ平和を願い祈るピアノ・バラードが、実に対照的に響き合い、映画への音楽演出として最良の効果を生み出していたのです。
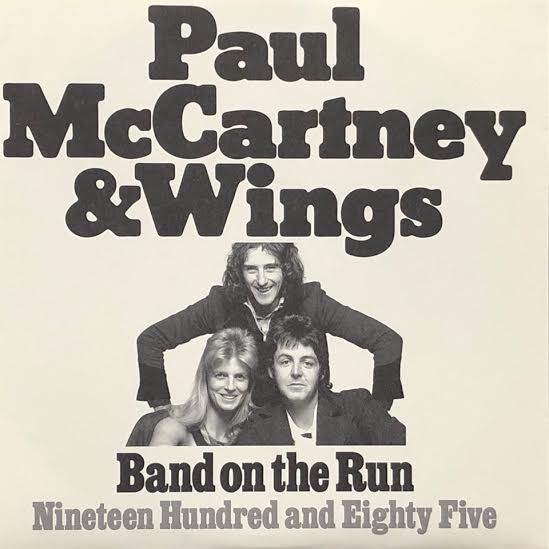

また、劇中音楽を「チューブラ・ベルズ」が映画『エクソシスト』(1973)に起用され、一躍映画界でも脚光を浴びた、マイク・オールドフィールドが手がけているということも特筆すべきところです。内戦という重々しい戦場という舞台に対して、賛美歌や、カンボジア周辺に位置するタイ、ベトナム、ラオスなどの民族楽器の特徴的なサウンドを取り入れながら、一種かなり独特な劇伴を作り上げています。特にエンドロールで流れる、フランシスコ・タレガの 「エチュード~アルハンブラの想い出」(スペインのギター曲)のカバー・トラックは本作のレクイエム的存在を存分に醸し出している見事なアレンジです。

後半、短調から長調へと押しあがっていく流れこそ、シドニーとプランが過酷な戦地から脱出し再会できたという、希望のメロディーに他ならないのです。
お次は、先ごろ4Kリマスターで再上映もされたイギリスのアニメーション映画『風が吹くとき』。

本作は、平凡な夫婦が核爆弾の放射能によってどんどん身体が蝕まれていくという、核戦争の恐怖を描くにあたり、直球でその悲惨さ、惨さを描き切ったという意味では、かなりの話題作であり、問題作でした。
こちらの作品の音楽を手掛けたのは元ピンクフロイドのロジャー・ウォーターズで、エレクトリック・ギターやサウンド・エフェクト、ダイアローグなどを駆使して構成したロック・オーケストラ調の各楽曲は、さすがかつてのピンクフロイドのフロントマン、かなり唸らせてくれるロック・シンフォニーに仕上げていて、ファンにも人気が高いサントラ・アルバムとなっています。

さらに表題テーマ曲を歌ったデヴィッド・ボウイの「When The Wind Blows」も秀逸です。
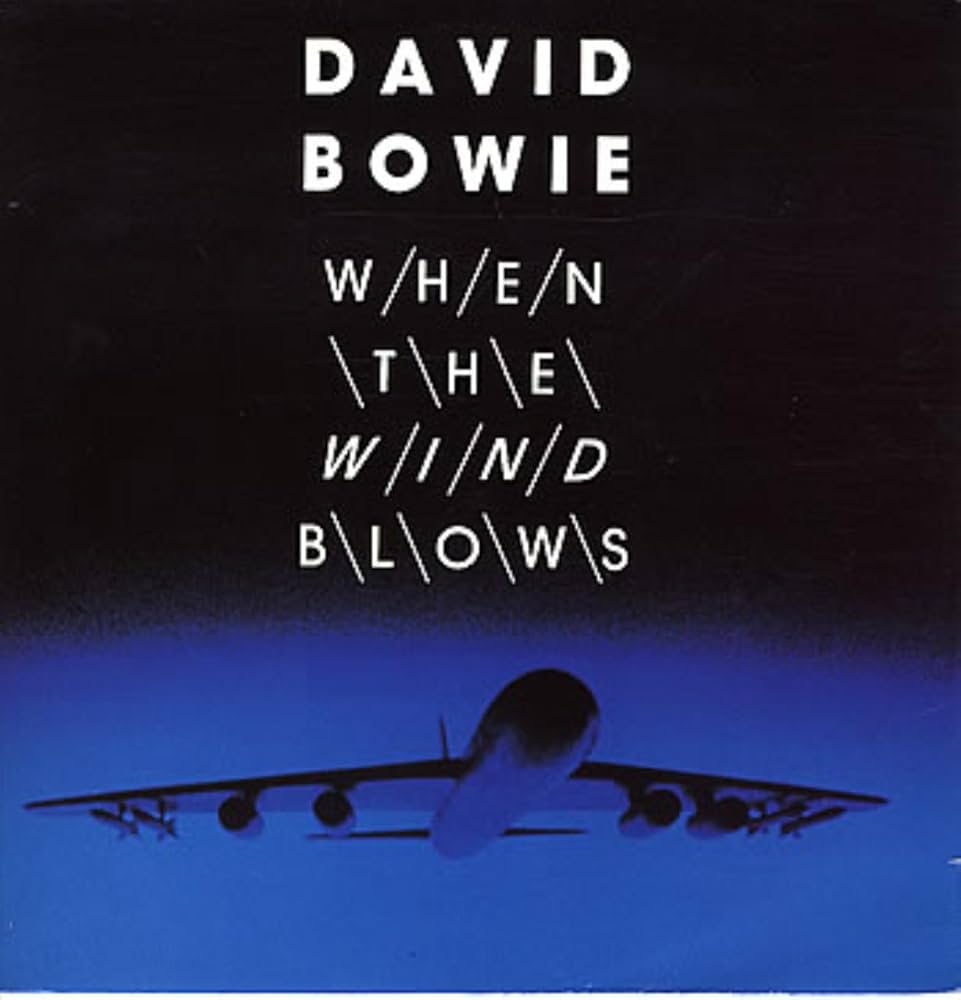
ヘヴィーなギターのリフが、壮大なオーケストレーションと絡み合い、この頃ボーカルをグッとロウ・キーに下げてドスの利いた歌声を披露していたボウイの、サントラ・ディスコグラフィーを代表する一曲となっているのです。当時人気だったミュージック・ビデオも劇中シーンとボウイ自身がアニメーションとなって登場し、それらがミックスして展開されることにより、核の恐ろしさ、それを食い止めていくということの必要性を感じさせる、とても斬新に作り込まれた傑作でした。80年代は、こうして常にサウンドとビジョンのミックスによってメッセージが発信されていましたが、当時はそれらを、多くの視聴者が同タイミングで共有していたということになるので、それはそれでとても重要なことだったと感じてしまうのです。
最後は日本映画から。こちらもアニメーション映画ですね。『この世界の片隅に』(2016)。

ご多聞にもれず、大ヒットアニメ映画となった本作ですが、戦争映画、反戦映画にして、戦時中の残酷描写などは一切なく、とにかくたとえ戦火に見舞われようとも淡々と家族の暮らしを守り、また営んでいく様が、これまでの戦争をテーマにした作品には無かった意外性と新鮮味を感じさせ、それらが戦時中のヒューマニズムを再発見するきっかけにもなり、大きな共感を呼んでいったのでした。
この作品の音楽を手掛けたのが、故・坂本龍一の秘蔵っ子、コトリンゴでした。シンプルなオーガニック・サウンドによる劇中音楽も素晴らしいのですが、何と言っても一番心に突き刺さるのは、ウィスパー・ボーカルのコトリンゴによってカバーされたザ・フォーク・クルセダーズのフォーク・トリオ・ソング「悲しくてやりきれない」(初出/1968)です。コトリンゴは既に自身の既発アルバムにて当曲をカバーしていましたが、この映画のために再度アレンジし直し(主人公すずさんの気持ちに寄せて)、レコーディングし直したといいます。この歌詞、悲しくて悲しくて、とてもやりきれない、という歌が流れるたびに、実際に主人公すずの心情が強く伝わり、映画の中の何気ないシーンでも、しっかりと映画のハイライトとなっていったのでした。

映画音楽を意識して戦争をテーマにした作品を観返すと、いかに作曲家やアーティストの皆さんが、とても真摯に、そしてとても繊細に楽曲を紡いでいることが伝わってきます。それらもまた反戦のためのメロディーたちなのでしょうね。
このサントラ、ちょっとレア。#00〜#32のオモシロサントラエピソード、まとめてどうぞ!
志田の映画音楽番組、湘南ビーチFM「seaside theatre」公式ブログはこちら。